
有元葉子さんの本 おすすめ8選

これまで有元葉子さんのレシピ本・エッセイ本をたくさん読んできました。
有元さんはすでに100冊以上の本を出されていると思いますが、その中でも私が特におすすめする有元葉子さんの本をご紹介します。
目次
レシピを見ないで作れるようになりましょう。
『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』(2017年発行・SBクリエイティブ)
最初に読んだ有元葉子さんのレシピエッセイ本。この本をきっかけに、有元葉子さんのレシピや考え方について知るようになりました。
『ごはんのきほん』『ふだんの洋食』がシリーズ本として出ています。
この本を読んで得たものや本の紹介は以下の記事で詳しく書いているのですが、簡単に言うと、私の料理観を変えてくれた革命的な本でした。この本のおかげで、料理が楽しいと感じるようになった。
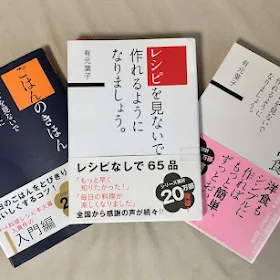
レシピを見ないで作るコツ。有元葉子さんのレシピ本から得たもの
レシピを見ないで作れるようになりたい方向けに、有元葉子さんの『レシピを見ないで作れるようになりましょう。』から学んだおいしく料理を作るコツを紹介します。
有元さんはこれまで数多くの本を出されていて、私もこの『レシピを見ないで』シリーズを読んでから、有元さんの本を片っ端から読みましたが、結局このシリーズ3冊に有元さんの料理観と考え方、選りすぐりレシピのエッセンスが詰まっていると思う。
未読の方にはぜひぜひおすすめしたい1冊+シリーズ2冊です。
だれも教えなかった料理のコツ
『だれも教えなかった料理のコツ』(2007年発行・筑摩書房)
料理の教科書を有元さんの著作から1冊選ぶとしたら、この本になると思います。
- 基礎調味料編
- 野菜編
- よくある材料編
- 魚介・肉類編
- だし汁編
- ごはん編
- 基本の調理道具編
という構成で、写真も多少は載っていますが基本的に文章で解説されているまさに教科書という雰囲気の本。
母に家で料理を教わらず、料理をきちんと習ったことのない私にとってはすべてがすべて、新鮮で勉強になることばかりでした。インターネットのレシピを参考に作るだけでは決して知ることができない、本当にだれも教えなかった料理のコツがまとまっている感じがします。
2007年の少し古い本ですが、料理を教わったことのない方にはぜひおすすめしたい1冊です。
基礎調味料編では、調味料の選び方と使い方に加えて有元さんが普段どの製品を使用しているかが紹介されているので、有元さんが使っているものを知りたい場合にもおすすめ。油も基礎調味料です。
野菜やお肉類の章は、素材別に有元家の定番料理や調理上の工夫が満載です。
調理道具に関しては後述する『有元葉子の道具選び』が一番詳しいのですが、この本では料理に最低限必要な基本の道具に絞って述べられていて、教科書的な感じにまとまっています。
〜勉強になったこと・心に残った言葉〜
- 酒は最初に、みりんは最後に加えるのが基本
- なすは揚げたほうが軽い仕上がりになる
- よい道具は料理の腕をぐんと上げる
はじめが肝心 有元葉子の「下ごしらえ」
『はじめが肝心 有元葉子の「下ごしらえ」』(2018年発行・文化出版局)
一般的なレシピでは省略されがちな「下ごしらえ」にフォーカスした本です。
本書では「下ごしらえは料理の9割くらいを占める」と述べられています。
また「下ごしらえにより、野菜は生き生きと、魚や肉は食べやすくうまみを引き出すことができる」「下ごしらえのしかたひとつで段違いにおいしくなる」と有元さん。
私は結婚してから料理を始め、3年ほどはクックパッドなどのインターネットレシピを見てその通りに料理を作っていただけで、下ごしらえのことなんてまったく知りませんでした。
レシピに書かれていることは書かれている通りにできるけど、書かれていないことは知らないしできない。そんな人間でした。
ちゃんと料理を習ったことがない私は青菜の処理の仕方とか、お肉や野菜の性質・切り方とか、恥ずかしくなるくらい何にもわかっていませんでした。笑
まぁ、それでもまぁまぁな料理はできていたと思いますが、この本の下ごしらえを知るだけで特に野菜はおいしく下ごしらえ&調理ができるようになったと思います。
野菜・肉・魚だけでなく、こんにゃく・豆腐・油あげ・乾物などのマイナー食材についても紹介されているのが良い。
〜勉強になったこと・心に残った言葉〜
- 「下ごしらえ力」は「料理力」
- 野菜は鮮度がいちばん大事
- 乾物は、いい状態のうちに下ごしらえをして、使いきることが肝心
有元葉子の道具選び
『有元葉子の道具選び』(2003年発行・幻冬舎)
有元さんがご自身の台所で使用されている道具がこれでもかというくらいに紹介されている本。調理道具屋さんを見て回るのが好きな方にはとっても楽しい本だと思います。
まな板は木に限るという話から、鍋、たまご焼き器、中華鍋、土鍋、クイジナート、バーミックス、木べら、お玉、スプーン、ゴムべら、しゃもじ、包丁、はさみ、チーズや大根のおろし金、粉ふるい、びわこふきん、、、などなどなどなど。
もうほんとに有元さんの家の道具ぜんぶ出してきましたみたいな感じ。
実際に使われている道具の写真と、なぜその道具が良いのかという有元さんの思いとこだわりが語られていて、なんかもうすみずみにまで有元さんの道具への愛を感じます。
私はコロナ禍のとき、料理がもっと上手になりたいと思い練習を重ねるなかで調理道具も見直すようになり、その際にこの本はとても参考になりました。
掲載商品そのものを参考にするというより、道具に対する考え方を知れるのが良い。
家庭で長年料理を作りさまざまな道具を使ってきた人の観点で、調理道具を選ぶポイントとそれぞれの調理道具の良さが書かれているので、それを踏まえて自分に必要な道具を考えたり選んだりできます。
こしょう挽きやびわこふきんなど掲載されている商品のうちいくつかは実際に購入したものもあります。
もう20年前の本なので、有元さんが現在は使用されていない道具も含まれるかもしれませんが、「考え方」に関してはいつまでも変わらないものだと思います。
なお、ラバーゼの製品はこの本の発行当時はまだ発売されておらず、ボウル・ざる・バットについては「使いやすいと思うものは今のところない」「理想のものを製作中」と書かれています。どのようなボウルが理想であるかについて厳しい条件が述べられており、その後ラバーゼとして発売されることになるボウルなどがこのとき試作されていたことがわかります。
この本を読んでなるほど〜と思っていた私は、その後ラバーゼのボウル・ざる・バットのセットを購入することになりました。

ラバーゼのボウルと角バットの使い方。使い勝手は極上!
ラバーゼのボウル・角バットのセットを購入して1年以上が経ちました。今回はこの8点セットを買った決め手と我が家での使い方、使い勝手を紹介します。
有元葉子の冷凍術
『有元葉子の冷凍術』(2022年発行・筑摩書房)
有元葉子さんが日々、どのような食材をどのように冷凍して活用しているかについて解説された本です。
まず取り上げられているのはだしとごはんの冷凍。
特にだしについては「煮干しだし」「かつおだし」「野菜のスープ」「鶏のスープ」などについて、だしの取り方、冷凍方法、解凍方法、活用方法までが丁寧に紹介されています。
私も日常的に野菜のだしを使ってスープを作っています。
関連記事

夜食スープに使える野菜だしの取り方と、毎日のスープづくり
ここ1年ほど、平日の夕食はスープ+白いご飯、もしくはスープのみという生活を続けています。そこで始めたのが、野菜のだし(ブイヨン、スープストック)を取ることでした。
ほかにも、「あると便利な冷凍素材」として、
- 肉(鶏手羽・鶏肉・豚肉など)
- 野菜(じゃがいも・かぼちゃ・トマトなど)
- 魚介(えび・いか・青背の魚など)
- 使い道が多い食材(パセリ・ホワイトソース・ひじきなど)
上記のような素材の冷凍方法・活用方法が解説されています。
ホワイトソースは冷凍の発想がなかったんですが、実際すごく使えます。グラタン好きなので、ホワイトソースを冷凍しておくと1人でもグラタン食べたいってときにとても便利です。
さらに、冷凍して保存できる料理としてロールキャベツ・ほたて缶シュウマイ・餃子・揚げ肉だんごなどのレシピが掲載されているんですが、
ここに書かれていた「シュウマイや餃子を角ざるに載せて冷凍する」というのが個人的にはかなり画期的だった!(角ざるはラバーゼから出ている四角形のざるです)
私はいつも作った餃子を冷凍する際、角バットの方を使っていて、角バットにくっつかないようにラップを敷いて餃子を並べて冷凍してました。。
角ざるであればそのまま載せてもくっつかずに冷凍できるのね、、、超便利じゃん。と大発見でした。
(有元さんは餃子は水餃子にして冷凍される旨が紹介されています)
関連記事

有元葉子さんの餃子を作ってみたよ。水餃子&揚げ焼き餃子で2回楽しむ
有元葉子さんの餃子レシピで水餃子&揚げ焼き餃子を作って食べました。皮から手作りし、作ったその日は水餃子で。残った餃子は茹でたあとに冷凍し、食べるときに揚げ焼きにしていただきます。
この本も、とにかく勉強になる1冊。最後に「冷凍庫を上手に使う16のポイント」がまとめられています。
〜勉強になったこと・心に残った言葉〜
- 冷凍かつおだしを使って自家製ポン酢やめんつゆを作る
- ホワイトソースの冷凍
- 有元さんは豆乳も冷凍
ちゃんと食べてる?
『ちゃんと食べてる?』(2012年発行・筑摩書房)
有元葉子さんが食生活の中で大切にしている基本的なこと、元気を与えてくれる食材、調理法での心がけ、などが紹介されているエッセイ本。
レシピもいくつか掲載されていますが、レシピ本というより「有元さんの食生活や日々の生き方」をエッセイとして読みながら、料理の基礎や調理法について学ぶという雰囲気の本です。
私は特に、
- 春夏秋冬でどのような野菜をどのように食べるか
- メープルシロップの効用や使い方
- 油の選び方や有元さんが使用されている油(ごま油・オリーブオイル)
についての章がとても参考になりました。
「ちゃんと食べてる?」は、有元葉子さんの公式サイトのタイトルにもなっている言葉。
「人を元気にするのは、まず食べ物から」ということで、おいしいものを食べることで心身ともに若くいられるし、結果的に健康でいられることになるんだよということですね。
〜勉強になったこと・心に残った言葉〜
- ごはんを自分で作るコツは、完璧にやろうと思わないこと。「これがおいしそうだから」と思えるものから始めればいい
- いちばん優先すべきは「今を充実して生きること」
- 水増し食品に注意
- 料理本のレシピはあくまで目安。上手になるにはくり返し作ること
- 揚げ物は失敗の少ない簡単調理法
パスタの本
『パスタの本』(2021年発行・東京書籍)
有元さんはパスタの本も何冊か出されています。イタリアにもご自宅があるため、パスタはすっかり日常食となっているとのこと。
『パスタの本』とはなんとも直球でわかりやすいタイトルですが、この本では作りやすく見た目も素敵なパスタのレシピがたくさん紹介されています。
- アリオ・エ・オリオのソース 20種
- 魚介のソース 8種
- トマトのソース 10種
- チーズ、バター、クリームのソース 13種
- ラグー 5種
- 手打ちパスタのレシピ
私が自分用に作るのはいつも簡単でおいしくて失敗のないトマトソースが多いです。
本書で紹介されている「生トマトソースのパスタ」はミニトマトを使ったパスタですが、ミニトマトだけなのにこんなにフレッシュでおいしく作れるのかーと結構感動する。別にベーコンとかもなくて良い。
あとは、トマト缶を煮るだけでできるトマトソースを使ったアラビアータとか揚げなすとトマトソースのパスタをよく作ります。
掲載されているパスタレシピのいくつかは『ごはんのきほん』にも載っていますが、こちらの本は写真付きレシピなので料理のイメージがしやすいと多います。
最近は YouTube やレシピサイトなどで、1つのフライパンでパスタを少量の水で茹で煮のようにしながらソースと一緒に作るレシピをよく見かけますが、有元さんのパスタレシピは王道で、大量の湯と塩でパスタを茹で、別鍋でソースを作り最後にあえるというものです。
使いきる。有元葉子の整理術
『使いきる。有元葉子の整理術』(2013年発行・講談社)
コロナ禍での生活中に刺さった本の1つ。有元さんがこれまでの暮らしの中で感じたこと、やってきたことが書かれています。
テーマは「片づけ」「整理整頓」「収納」「家事の進め方」「掃除」で、料理本というより生活本と言えます。
私は未熟なので掃除とか整理整頓とかそういうテーマにはまだ興味を持てなかったんですが(笑)、本書で一番興味深かったのは「家事の「流れ」を作る」の章。
特に「台所には台がないとだめ」「空きスペースがないとだめ」みたいな話は、調理道具の収納やキッチンスペースの有効活用について考えたりするのに参考になりました。
また、ふきんの運用についても勉強になりました。
ふきんについては『有元葉子の道具選び』他複数の本で触れられていますが、本書でも「ふきんがなければ始まらない」と紹介されています。
和太布ふきん、びわこふきん、その他さらしのふきん、かやふきん...と、どういったふきんをどのように使うか。使い終わったふきんをどう処理するか。
コロナ禍にこの本を読んだ当時、私は水切りかごなしで「洗った食器をふきんですぐに拭く」ということをやっていて、ふきんについてはどんなものを使うか、使ったあとに濡れたふきんをどうするか、使ったふきんをどう洗うか、みたいなことをよく考えていたんですよね。
この本を読んで、和太布ふきん、びわこふきんを使うようになりました。
ふきんを重要なものとしてここまで言及される料理研究家の方はなかなかいないのでは。さすがだと思います。
〜勉強になったこと・心に残った言葉〜
- 衣類でも寝具でも台所道具でもなんでも、自分に本当に合うものって、そんなに多くない。限られたものを最後までとことん使いきる
- 器の収納で一番大事なのは「空き」を作ること。器の数を減らしてでも「空きを作り出す」のが重要
- 料理も家事も人生も大事なことは一緒。要は自分を使いきること
まとめ
こうして挙げてみると、私が有元葉子さんの本の中でやっぱり参考になるなと思うのは「基礎の本」「考え方の本」だなと感じます。だから今回紹介した本も、内容的にはちょっと偏っているかもしれません。
有元さんはレシピ集的な本も多く出されていて、私もレシピ本はいろいろ見たんですが、夫婦2人暮らしで来客のない我が家では出番がなさそうな料理だったりレシピ自体が難しそうだったりするものが多く、眺めるだけなら楽しいけど「日々の料理の参考にする」という点では難しいなという印象のものが多かったです。
(ここで私が挙げているレシピ本は、そんな我が家でも使える素朴な日常料理のレシピ本です。来客が多いお家だったり、本当に料理が好きという方には、その他の有元さんのレシピ本もとても参考になると思います)
レシピ本ではなく「基礎の本」「考え方の本」は、料理を真似するというより考え方を取り入れるという感じになるので、どんな料理を作る上でも参考にしやすく、どういうお家でも汎用性の高い内容なんじゃないかなと思います。

有元葉子さんのおすすめレシピ
今回は有元葉子さんのレシピの中で、私のお気に入りレシピを7つ紹介したいと思います。どのレシピも難しくなく、誰でもおいしく作れるものです。







