
『検察側の証人』ショッキングすぎる結末に呆然~アガサ・クリスティ

アガサ・クリスティの『検察側の証人』は、もともと『死の猟犬』という短編集に小説として収録され、その後戯曲として書き直された作品です(1953年初演)。
訳者あとがきには、「彼女の戯曲としては最高傑作と言えるだろう」と書かれています。
この作品は、先日読んだアガサ・クリスティの戯曲『招かれざる客』で受けた衝撃をさらに上回ってくる衝撃を与えてきて、読後はほんとショック状態でした。
先日 M-1 グランプリが放送されて、ファイナルで決勝の面白さを超えないとグランプリは取れない、決勝が良ければそれだけファイナルへの期待値も上がる、順番も大事、みたいな議論があったと思うんですが、これ、今回の読書はまさにソレ。
たまたま『招かれざる客』→『検察側の証人』という順番で読んだのも良くて、最初に『招かれざる客』でまず面白くて満足し、次はどんな話が読めるんだろう?とワクワクしながら『検察側の証人』を読んでみたら、さらに期待を超えてきた。
これはグランプリ。アガサ・クリスティ優勝。拍手。
『検察側の証人』あらすじ
弁護士ウィルフリッド卿の事務所に、ある殺人事件の重要参考人となっている青年レナード・ボウルが相談にやってきた。
事件の被害者は50代の裕福な独身女性。レナードは一か月半前から彼女と親しくなっており、事件が起きた晩にも女性の自宅を訪れていた。
レナードは既婚者だったが、いつも1人で女性のもとに通っていた。レナードは失業中の身で、お金に困っていた。その女性は殺される直前、全財産をレナードに譲るという遺書を残していた。
状況証拠は彼に不利なものばかり。動機もある。警察はレナードを殺人犯として追っていた。
事情を聞く弁護士に対して、レナードは自分はやっていないと主張する。犯行推定時刻には自宅にいて、妻のローマインなら自分のアリバイを証明してくれるという。
だが裁判に証人として出廷したローマインは、レナードを愛したことは一度もなかったこと、夫からアリバイ工作を頼まれたことなどを、検察側の証人となって証言するのだった......。
街で知り合い親しくなった金持ちのオールドミスと青年レナード。ある夜そのオールドミスが撲殺された。状況証拠は容疑者の青年に明らかに不利。金が目当てだとすれば動機も充分。しかも、彼を救えるはずの妻がなんと夫の犯行を裏付ける証言を……展開の見事さと驚愕の結末。裁判劇の代表作。(解説 菅野圀彦)
『検察側の証人』(早川書房 クリスティー文庫)
以下はネタバレを含む感想です。
『検察側の証人』のすごさと感想(ネタバレあり)
この作品のどこが一番すごいのか。
ローマインの「妻であり外国人である自分の発言は信用されない」という自覚に基づいた証言と手紙の工作、レナードの正体、ラストへの持っていき方、まぁすべてが衝撃的なんですが。
私は、ローマインが最後に「自分が偽証罪で裁かれることはない」と言った通り、裁判で偽証となるような証言を一切していなかった(と思われる)構成になっているのが一番すごいと思った。
レナードは犯行を否定しているにも関わらず、裁判でローマインは次々とレナードに不利な証言をしました。
「レナードが戻ったのは十時十分過ぎ」(犯行を終えて帰った時刻と合う)
「レナードは血のついた上着を洗ってくれと言った」
「レナードは彼女を殺したと言った」
「レナードに九時半に家にいたことにするよう頼まれた」
「最初の警察の尋問にはレナードの指示通りに答えたが、事が人殺しだったために裁判では真実を言うことにした」
「レナードはわざと自分で手首を切った」
このときまでにウィルフリッド卿も読者もレナードの話を信じ込まされているので、ローマインの証言のほうを嘘だと感じるようになっているが、実はこれらすべてが真実だったという話。
ローマインは、レナードが犯人だという真実を語りながら、(自分の偽証罪と引き換えに)レナードの無罪を勝ち取るという筋書き。
すごすぎませんか。
作中にはローマインの証言通りの事実があったという明確な描写はないが、あれだけ偽証罪の宣誓が強調されていること、マイアーズ検事が「天地神明に誓って事実なんでしょう?」と聞き「間違いございません」と答えていること、偽証罪にはならないとローマインが最後に言っていること、ローマインの性格、レナードが犯人だという結末を考えあわせて、あの証言は事実だと考えて良いと思う。
手紙が持ち込まれたあとの証人喚問では、ローマインは最初「手紙は書いていない」と言っていますが、最終的には自分が書いたと認めてるのでここも偽証にはならないでしょう。
最初の証人喚問で発言した「レナードを愛してはいない」というのは、結末からすると噓だったことになりますが、感情は証明できないですからね。
いやー、すごすぎる。
序盤でたぶんほとんどの読者の頭が「レナード≒無実」になっているので(ウィルフリッド卿も同様)、客観的にはローマインの証言が嘘だと信じる理由は何もないのに嘘だと思わされてしまうという。
丁寧に読み返すと、マイアーズ検事もちゃんと「本証人が真実以外のことを述べていると思われる節はまったくありません」と発言しているんですけどね。ほんとそれ。
でもウィルフリッド卿と読者の思考としては、なぜローマインはこんな嘘の証言をするのか! 妻なのに! あれだけ偽証罪の脅しをかけられていながら! 一体何を狙っているのか! という方向に進んでいく。
そこからの匿名の女による手紙からの、裁判での逆転劇からの、ローマインの意図とレナードの犯行の暴露。
まさかローマインがレナードの犯行を知ったうえで、愛する夫のために無罪の獲得を狙っていたとは。
想像を超えすぎています。
もうひとつ感想としては、レナードが信じがたいほどクズでつらい。
遺産目的で独身中年女性に思わせぶりに近づき彼女を殺しておきながら、自分はやってないと弁護士たちを欺いていたうえに、助けようとした妻のローマインをも裏切っていて若い女と一緒になろうとしていたというのがショッキングすぎて呆然。
「この娘はな、お前なんかより十五も若いんだよ。(と笑う)」
(と笑う)ってなんだよ、アガサ・クリスティよ。
レナードが刺される結末は良いんですが、これじゃあローマインが裏切られたうえに殺人罪になってしまってまったく報われない。
1953年の本作品発表時、イギリスでは殺人罪は基本的に死刑。1957年に死刑となる殺人の種類が限定され、1965年に死刑廃止。
あのイチゴ・ブロンドに刺させるか、交通事故とかにしてほしかった。
読み返してみると、レナードの正体の一端は序盤でローマインがウィルフリッド卿の事務所を訪れたときの会話からも想像できます。
裕福なフレンチおばさんが財産をすべてレナードに譲ったということに関して、ウィルフリッド卿がローマインに「御主人にしても、まったく思いがけないことだったんじゃないんですか?」と聞くと、ローマインは間を置いてから「主人がそう申しましたの?」と意味深に答えています。
レナードが遺産を譲らせるつもりだったことは、ローマインにはバレてるんですね。
また「御主人を自分の息子か、お気に入りの甥かなにかのように思っていたことは間違いないようです」との言葉には、「ずいぶん偽善者ですのね」と発言する。
ここ、最初はどういう意味なのかよくわからずスルーしてたんですが、フレンチおばさんは当然レナードを結婚対象の恋人として見ていたし、レナードも当然思わせぶりにフレンチおばさんに接していた、とローマインは理解していたということですよね。
偽善者と言っているのは、レナードのことはどう考えても年若い愛人のような存在と捉えてしかるべきなのに、母親にとっての息子のような存在だと無理やり健全に考えようとしてるのね、というローマインの皮肉。
レナードがフレンチおばさんに対して既婚者であることを伝えていたかは、家政婦ジャネットの言う通りかなり怪しい。いや、まぁ普通に考えて独身だと偽ってたでしょう。
ローマインがウィルフリッド卿の事務所を訪れたシーンの描写は、結末を知ってから読むといろんなことが読み取れて面白い。
最後に白状すると、私はアガサ・クリスティのことだから真犯人は全然思いもよらない人だろうから、ウィルフリッド卿かマイアーズ検事が犯人なんじゃないかと根拠もなく思いながら読み進めてました。。
レナードが犯人かもしれないとは最後まで1ミリたりとも気づかず。完全に目曇ってましたね。
『招かれざる客』はアガサ・クリスティの戯曲の面白さを教えてくれた作品でしたが、『検察側の証人』はさらに上をいく作品でした。
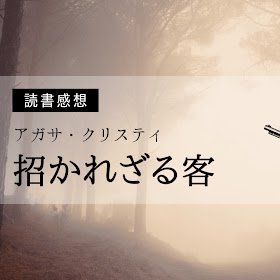
『招かれざる客』読みにくさを超える戯曲!アガサ・クリスティ
台本の形式で書かれている戯曲は読みにくいものですが、アガサ・クリスティの『招かれざる客』はその読みにくさを軽く超える、非常に面白い作品。出だしから読者の興味と好奇心を最大限に引き出してくる一冊でした。

 www.limosuki.com
www.limosuki.com